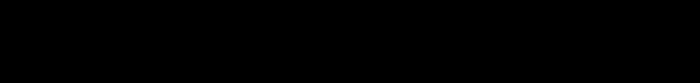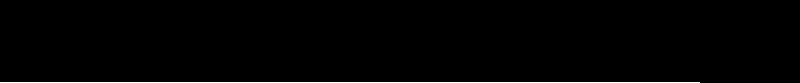

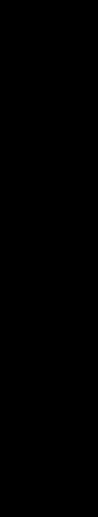
こんばんは。 W. E. F. U. N. K.ステーションへようこそ! We-Funkの方がわかりやすいかな。
|
||||
■ ライディーン / YMO 「てーれーれー てれれ れってれ れってってー」 YMOこそがイエロー・ミュージックというものの存在を世界に気付かせたバンド、というのはまず間違いない。デトロイトテクノ、ニューウェーブ〜マンチェ、国産歌謡などのシーンは言うに及ばず、バンバータ経由の Riot in Lagos でヒップホップにも大きな影響を与えた。シュトックハウゼン、シューカイ、クラフトワークらドイツの前衛家らの音楽を咀嚼し、高品質大衆音楽に落とし込んで再プレゼン、という手法も、いま考えてみれば実に日本人らしい。 ちなみに世代的に言うと、80年生まれの僕にとってYMOはぜんぜん同時代じゃない。周りが X JAPAN や Mr. Children の台頭に熱狂していく中、それへの反発と雑誌で見る「お兄さん世代」のサブカル趣味に憧れて、たぶん「テクノデリック」あたりから聞いてみたのだが、まぁ意味が分からない(笑) それはなぜかというと、前衛的なことをやってはいるんだが、シンセの音色自体はすでに90年代に入り急速に陳腐化していた、そのズレだったんだと思う。はじめてYMOに夢中になれたのは、1stアルバムを手に入れてからだったと思う。
|
||||
| ■ バトル・アゲインスト・クラウン / 芸能山城組 「どっどー ひーはーひーはー」 そういう意味で映画「AKIRA」の音楽は実に強烈だった。もちろんコレも88年公開だから微妙にコンテンポラリではない。しかし、中学生のころビデオか何かで見て以来「声をリズム楽器として使う」「西洋音楽でもポップスでも民族音楽でも無い何か」という発想に夢中になり、そのころ出来はじめた新古書店を漁った。 芸能山城組は山城祥二こと農学者/音響学者/その他もろもろ/芸術家の大橋力が設立した、素人による芸能集団。元はただの東京教育大とお茶の水女子大の西洋混声合唱団だったらしいが、66年に山城が指揮者として就任し、民族音楽学者小泉文夫の指導を受けるうち、ブルガリアンボイスやホーミー、唱名、民謡、ケチャ、ピグミー唱法などをレパートリーとして持つ特殊合唱団に。 ちなみに大橋力は東北大の博士論文で麦角アルカロイド(要するにLSD)の研究を行い、筑波で講師になってからはKJ法の川喜多二郎と親交を深め、80年代はバリなど世界各国に民族音楽の調査に出かけつつガイア仮説っぽいことを唱えてみたり。90年代に徐々に音響と脳機能方面へ転換、2000年に不可聴高周波でのトランス導入についての論文を発表したりしている。典型的なニューエイジマッドサイエンティストの経歴で最高。
|
||||
| ■ 飛べないモスキート (MOSQUITO) / 桑田佳祐
「暗い教室の隅で彼は泣いている」 サザンの享楽的なサウンドよりも、桑田個人/KUWATA BAND の内省的で攻撃的な曲の方が良いに決まってるぜ! とか言いつつやっぱり新古書店で漁ってました。中二病ですね。これはいじめられっこやら、弱者についての歌なんだが、まぁいじめられっこのおれにはジャストミートだったわけ。サザンでは前面に出さないブルージーな曲調にもまたハマって、アメリカ音楽のルーツに目ざめさせられたのは桑田がいたからかも。 ただ、今考え直してみると、ちょうどいじめと自殺がマスコミをにぎわしてたころでもあり、この内省や同情のまなざしにすら「時代の託宣者」桑田の嗅覚を感じる。桑田……おそろしい子!
|
||||
■ 夏の日の午後 / eastern youth 「まだ生きて果てぬ この身なら 罪も悪も我と共に在りて」 そして某DJと同じく、おれもまた井上貴子のミュージックスクエアのヘビーリスナーだったわけで。そこではじめて「耳だけで」衝撃を受け、購入を決意したアーティストがイースタン。佐伯祐三画伯ジャケアルバムの1曲目がこの曲です。当時ラノベ脳だったおれは「少し日本語詞として仰々しすぎるかな」とか思っていたのだが、年を重ねれば重ねるほど、吉野の言葉が身につき刺さってくる。 20世紀末のあのころロックにはまった人の主流は3つくらいあって、ジュディマリ・ミスチルらのポップ路線、黒夢・ラルクらのビジュアル系、そしてハイスタ・ブラフマンのメロコア。だいたいのロック好き=音楽好きはこの3つのどれかに所属していた。でも、それらにどうしても違和感を見出してしまう文系童貞ハードコアとでもいうべきマイナたちが一定数いて、イースタン、エレカシが彼らの心のヒーローだったように思う。
|
||||
| ■ 東京 / くるり
「じゃーんじゃーんじゃ じゃじゃじゃじゃじゃーじゃじゃ じゃーんじゃーんっじゃっ っ じゃっじゃーん」 そうした文系童貞ハードコアが待ち望んでいた同世代バンドが、くるりだった。いかにもモテなそうな風貌(今の状況からはとても想像できないことだが!)、屈折した暴力性を放つギター、地方出身。おぼえているだろうか。あのころ、くるりに対するロキノンの定番形容詞は「変態」だったのだ。
|
||||
| ■ ガストロンジャー / エレファントカシマシ
「お前そんなの百年前から誰でも言ってる。あぁ?お前変わんねえんだよお前ソレお前」 BPM150のエレクトロニカビートに乗せた、ブルドーザのようにひたすら進むアジテーションと、必殺のユニゾンシンガロング! 綿菓子みたいなドラマ主題歌、そして飼い殺しに苦しんだポニーキャニオンから、東芝EMIへ移籍後の第一弾シングルなのだが、もうポニキャニ時代の鬱屈と怒りをすべてぶちまけたような快作。日本から唯一レイジに回答できた作品とも言える。 以後、宮本は「我々は、社会はなぜこんななのか」というロックにおける大きな命題に対する補助線として、自覚的に歴史、とくに近現代史へのまなざしを求め、文系童貞ハードコアの中心をになっていくこととなる。
|
||||
| ■ Strings of Life / Derrick May
コピペ貼っておく
|
||||
| ■ Wack Wack Rhythm Island / Wack Wack Rhythm Band feat. Rhymester
「帰りたくないならリピート Sayあと1曲!あと1曲!」 2007年に出たライムスター外仕事ベスト盤「BEST BOUTS」のセルフライナーで「本人たちが知らないところでクラブヒットしてた」とか何か書いてた気が。今思えばダフト「One more time」に対する2000年代前半東京クラブシーンからの返歌だったのかも。ワックワックリズムバンドは元フリーダムスイート(島田正史とチャーベも所属した渋谷系モッズバンド)、“渋谷系のポール・ウェラー"こと山下洋が率い、渋谷INKSTICKを根城に活動する10人(くらい)編成のインストソウルバンド。
|
||||
| ■ P-Funk (Wants To Get Funked Up) / Parliament
「I want the bomb, I want the P.Funk I want my funk uncut.」 これはもちろん「Live: P-Funk Earth Tour」から。史上最高であり、おれランキング最高のライブ盤。持ってないヤツはファンク好きどころか黒人音楽好きを名乗る資格がない。聴け! 盗ってでも聴け! というレベルの名盤のオープニングを飾った、間違いなく音楽史に残る1曲。 超絶倫的な焦らしのテクニック、セクシーというかセックスそのもののフレッド・ウェズレイ&メイシオ・パーカのホーン、胸にからみつくギターとキーボード、体をゆらす鼓動。ジョージ・ブッシュよりヒラリー・クリントンより5万倍は激しく、4980億倍は説得力のあるジョージ・クリントン船長のアジテーション。そして何よりLAフォーラムにできた、うねる黒い海が眼前に見える! そうこのライブアルバムが世界一なのは、客が世界一エキサイトしてるから! 焦らされまくった観客にみなぎる期待感と緊張感、そして我らのマザーシップから降臨したジョージ・クリントン導師の一声で瞬時に爆発する熱狂の肉体言語! これが音楽。これこそがダンスミュージック。
|
||||
| ■ ナーダム / 渋さ知らズ
「おーおーおーおー おお おーおーおーおー」 残念ながらおれはP.Funkを現役で体験できなかった。けどおれには渋さ知らズがあった。ライブ行かなきゃはじまらない。集団グルーヴファンクってそういうものです。行って白塗りダンサーに笑い、ミニスカに煽情され、ステージに蝟集するスゴ腕ミュージシャンのソロにしびれ、それを操作するダンドリスト不破大輔の後ろ姿に一体化し、声を限りにシンガロングする。 渋さの絶対的なユニゾンの魅力は、じゃがたらの篠田昌已の教えであり、アケミが日本のメイシオだったら渋さはやっぱりP.Funk。ちなみに渋さオリジナルではなく、作曲は山下洋輔バンドのサキソフォニスト、林栄一。
|
||||
| ■ 元気でやってるのかい? / イルリメ
「うたに込めた思い出一つ 胸の中では・じ・け・ろ!」 おれが今いちばん信用しているうたいて。それがイルリメ。関西スカムにも、日本語ヒップホップにも、関西0世代にも、テクノポップブームにも、エレクトロニカ再興にも、下北にも、中野にも、すべてに人なつっこく顔を出し、すべてに染まらず立ち続ける男。ネタを愛しても笑いきれない、悲しき関西弁野郎の自由。00年代最高のアルバムが「イルリメNo. 5」であることに異論のあるヤツはおれんとこ来い。
|
||||
| ||||