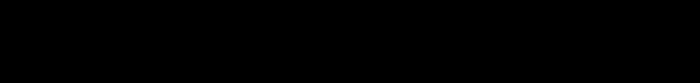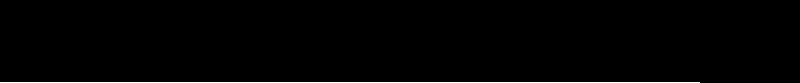

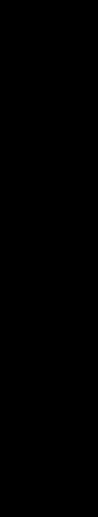
|
||||
■ 24時間の旅 / The Boom 自分の意志で初めて行ったコンサートはTHE BOOMだった。島唄より数年後、彼らが意識的にさらに南のアジアや南米の音楽を目指し始めた頃。ミヤさんの「欧米ばかりが海外かい?洋楽かい?」という問いかけは、まだ14,5の自分にかなりの衝撃を与えた。 世界を股にかけたツアーを行い、15年の活動にひと区切りをつける武道館ライヴで配布されたのは、どんな空の下でも朝の光は旅の始まりなんだ、と高らかに告げる曲だった。
|
||||
| ■ Every Single Day / Love Love Straw 新任の先生が自己紹介の時に「僕、バンドやってるんですけど」ってバンド名を板書するなんて、どんなに幸せな出会いだと思う?少なくとも、ワタクシにとってはその後の人生を180度変えた瞬間だった。インディバンドとの出会い、「コンサート」ではなく「ライヴ」との出会い、下北沢という街との出会い…。 まさに(あらゆる意味で)恩師と呼ぶべき彼らのメジャーデビューシングルは、80年代アイドル歌謡によって育まれたメロディセンスを、90年代初頭のUKロック的なセンスとめいっぱいの爆音で包み込んだ、抗いようのない名曲。
|
||||
| ■ Raspberry / Triceratops
16歳、初めてひとりで行ったトウキョウ、渋谷タワレコで買ったCDはトライセラ。試聴機の下向きヘッドフォンに戸惑いながらも、イントロのワンストロークで胸を撃ち抜かれた衝撃を今でも思い出せる。 シンプルなコード進行にタイトなリズム、甘え上手なわっしょーの歌声もベッタベタに甘い歌詞もいいじゃない。ひとつの恋がはじまってどうにも落ち着かない気分の時は、いつもこの曲をくちづさむ。
|
||||
■ Cellophane / ヨアケ・ハナビラ 「センスはいいけど、どこか優等生ギミなギターバンド」だった彼らが、サポートキーボーディストの加入を機に、まったく別の力強さと技巧に優れたバンドに生まれ変わった記念すべき曲。 従来から持ち合わせていた抜群のメロディセンスに、変則的な楽曲の構成、プログレバンドか!?と見まごうばかりの即興的で奔放なライヴパフォーマンス。「同じ曲をライヴrecとスタジオrecの2パタン収録した」最後の作品は、彼らのライヴに対する圧倒的な自信の現れだろう。あの緊張感溢れるライヴをもう見る事が出来ないと思うと、とてもさみしい。
|
||||
| ■ くるり / ワールズエンド・スーパーノヴァ
真夜中の研究室とハンダの焼けるにおいと明け方の467号線。研究に没頭する、というと聞こえはいいけれど、実のところ家主のように住み着いている人に夢中なだけだったかもしれない。 どぷりとした暗やみのように重たくうねるハウスビート、そこから時折こぼれ落ちるのは超新星の煌めき。ブリッジの「いつまでもこのままでいい?」という問いかけに涙したのも、もうずいぶん昔の話。
|
||||
| ■ 中村一義 / キャノンボール
「僕は死ぬように生きていたくはない」
|
||||
| ■ Gash / 窓
「ゆめゆめ忘れないで 窓は閉めないで」 初めて行ったライヴの、1曲目の歌い出しで完璧に恋に落ちた。ノエル&リアムに匹敵する兄弟喧嘩を幾度となく繰り返す石塚兄弟がフロントを務めたバンド、Gash。19歳からの4年間は下北沢という街で、常に彼らの息づかいを感じながら過ごすことになる。 ライジングサンに無謀にも18きっぷでむかったのも、ハイエースに揺られて全国津々浦々のライヴハウスをを駆け回ったのも、兄弟喧嘩に釣られて深夜に激高したのも、彼らの奏でる音がなにより誠実で愛に溢れたものだったから。
|
||||
| ■ Scudelia Electro / Day After Tomorrow
石田小吉というひとが自分の人生に与えた影響はあまりにも大きい。単なる「好きな音楽家」というよりは、厳格な父親だったり、気ままな隣人だったり、凝り性の兄貴だったりする。 彼のふたつめのキャリアから、千本浜に沈む晩夏の夕日と夜空を描く歌を。「エレクトロとロックの融合」なんて最近騒がしいけれど、思えば彼らは10年以上前から当たり前のようにそうだった。彼のうたう暮れの情景は、いつも少しだけなつかしくて切ない。
|
||||
| ■ Spitz / アカネ
茜色の空に、来るべきあしたへの決意を秘めた歌を。キャリア随一のロック・アルバム「ハヤブサ」の最後を飾るこの曲は、駆け足のようなビートに乗せてひとつの終わりとはじまりを歌う。 陽はのぼりまた繰り返すのだし、流した涙は拭わずともいつかは乾く。「お葬式の出棺、クラクションキッカケで流してください」と遺言状に書きたいくらいの力強さといたわりとあたたかさを持った名曲。
|
||||
| ■ CHAGE&ASKA / 告白
意識的にひとつのアーティストを聞き込むようになったのは11才の頃、チャゲアスに夢中になってから。あまりにもヒットしたシングル曲イメージが強いけれど、ビートルズからの影響を隠さないソングライティング、複雑に入り込んだふたりのハーモニーの巧みさには、じつのところかなり大きな影響を受けている。 この曲はSAY YESのカップリングに収録されたのみの、密かな名曲。タイトルチューンはアスカがあれだけ朗々と愛を歌い上げているのに、こちらでは片思いの静かな熱情をいじらしくチャゲさんが歌うのだ(チャゲに「さん」をつけてしまうのは間違いなく火曜ミリオンナイツの影響)。 |
||||
「あの夜から僕はうまく眠れない あなたにすべてが吸い込まれてく」 そう、オンガクに恋をしたその時から、もうずっとぼくらは彼らのトリコなのだ。
| ||||