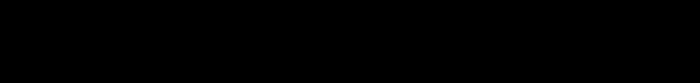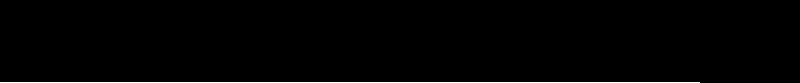

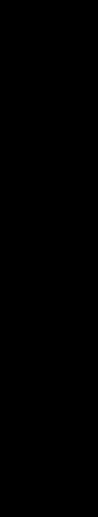
|
||||
■ 今夜はブギー・バック (smooth rap)/スチャダラパーfeat.小沢健二 EAST END×YURIの「DA・YO・NE」と共に、日本のヒップホップが市民権を得るという点において記念碑的な曲。ヒップホップ原体験となった「とにかくパーティを続けよう」というあまりに高い熱を放つ歌詞と、どこかひんやりとした都会の空気を持つビートの出会い。 三つ子の魂百までとはよく言ったもので、今でもヒップホップに触れるときはメロウなビートに惹かれる。 派手なパフォーマンスは、熱を伝えるために必須の要素ではない。
|
||||
| ■ We Are The World/USA For Africa 一方で、派手なパフォーマンスは武器にもなりうる。アメリカ人はチャリティーが好きだ、という話は既知の事実。その動機はより大きな名声を得るためでもあるだろう。しかし、それでも結果として多くの命を救うことに寄与しているという点を見逃してはいけない。 力を持たない者しかできないことがあり、力を持った者しかできないこともある。後者を地で行く80年代スターが一同に会した、奇跡の一夜を真空パックにした本作。クインシーのプロデュースと、シンディのシャウトに当時の空気を感じる。
|
||||
| ■ 東京/くるり
ひねくれ者でありたいって思っている人が嫌いだ。だけど翻って考えると、ひねくれ者であるための方法論こそが、この曲に最初に触れた当時の行動指針であった気がする。遠回りな言い回しや、言葉とは裏腹の態度。でも、本当は「ついでに」なんかじゃなくて、君に電話したかった。「君と上手く話せるかな」というのが、心の奥底では中心にあった。 くるりは常に、日常の何気なくて、しかも小さな小さなひとコマを歌う。「ウィーザーとレディオヘッドを混ぜたみたいな曲」にこの歌詞を使わない手はない、という彼ら自身の弁が現す事実は、彼らが本物のひねくれ者であるということ。
|
||||
■ Stay Gold/Hi-STANDARD 自分がひねくれ者になれなかった、ということは小さな挫折ではあったが、悲観するものではなかった。むしろその道を通ったこと自体が、今となっては大きな財産だ。 迷いながらも色々な道を模索していた1999年。時を同じくして、傷つき、立ち止まり、迷いながらもメロディック・ハードコアというシーンに大きな道を作った彼らは、AIR JAMを最後に2000年、活動を休止する。
|
||||
| ■ 世界の終わり (primitive version)/Thee Michelle Gun Elephant
限界に触れる機会は貴重だ。肝が据わるし、何より自信につながる。但し、限界点を見極めることは簡単なことではない。ここが限界、そう自ら判断した更に2歩先に、本当の限界が見える。そこは開放された世界。全てを受け入れ、また許せる世界。 あのとき触れた限界が、確かに今の糧となっている。
|
||||
| ■ 君ノ瞳ニ恋シテル/椎名林檎
彼女の魅力は巻き舌に拡声器、ちょっと前ならそう言い切っていただろう。確かに拡声器を片手に、舌を巻いて歌謡曲的ファンクを歌いこなす彼女は、とても魅力的だ。でも、彼女の最大の魅力は、軸がぶれない強さを持っているところにある。 「勝訴」発表後の彼女は、彼女に対し余りに固定観念を持った人を恐れた。それでも彼女は、強さを失わず、より自分そのものを見せつけることに成功した。軸を持っていたいと思う。どんなときでも、ぶれない軸を。
|
||||
| ■ Electronic Battle Weapon 10 (Midnight Madness)/The Chemical Brothers
「Surrender」が発表されたとき、初めて存在を知った。しかも音を聴いてというより、Kate Gibbがデザインしたジャケットに惹かれて、CDを手に取った。彼らは所謂ビッグ・ビートの生みの親であると言われているが、その言葉を知ったのは、それから随分後のことだった。 しかしロック・ミーツ・テクノであるビッグビートが、ロックに慣らされた自分の心と体をこの上なく刺激することとなったのは、必然であった。 駆け上がっていく音の束は、星が輝く午前3時が良く似合う。
|
||||
| ■ Perfect Storm/KAGAMI
刻々と位相を変えていく音像。それはテクノの大きな魅力のひとつだ。しかしKAGAMIの作品には、いくつかのループとエフェクトで一発勝負という作品が存在する。ともすれば単調とも捉えられかねない曲調。 その中で、6分強という尺を最後まで踊らせるエネルギーの源泉は何か。答えはダンス・ミュージックを聴く者が体で覚えた、いわば王道とでも言うべきパターンを確実に踏襲した曲である、というところにある。王道、故に無敵なアッパー・チューン。
|
||||
| ■ 虹/電気グルーヴ
星降る夜も、雨降りの朝も、嬉しさや悲しさも。全てを通り越したら、光が射して、虹が出た。使い方によっては安っぽくて薄い響きになるセンチメンタルという言葉だが、この曲にはセンチメンタルという言葉しか当てはまらない。 電気グルーヴといえば、人を食ったようなタイトルやトラックをイメージするかもしれないが、それはひとつの側面でしかない。むしろ彼らの本質は、この「虹」や「ナッシングス ゴナ チェンジ」に代表されるセンチメンタリズムにあるような気がしてならない。バカ騒ぎは涙の隠れ蓑。センチメンタルの、全てがここに詰まっている。
|
||||
| ■ Viva La Revolution/Dragon Ash
「常にカウンターでありたい」と言い放った降谷建志が、カウンターのまま自らの存在を世間に認めさせたのが、本曲を含む同タイトルのアルバム。彼が戦う相手として見つめていたのは個人ではなく、常に社会全体であり、また自分自身であった。だからこそ「Grateful Days」で共演したZEEBRAから個人攻撃を受けた彼は、大きなショックを受けた。 自分に自信を無くしたとき、割れた音を耳に浴びせながら、自分と向き合い続けた過去がある。これからも自分が自分であるために、この曲を聴き続けたいと思う。音が割れないように、あのころより少しだけヴォリュームは小さくして。
|
||||
出身地も年齢も、音楽の嗜好ですら十人十色。共通点はただひとつ。それは音を愛し、人を愛しているということ。ひとつでも、ひとりでも多くの音や人に触れに来てみませんか。
|
||||